都市と文化を一体で捉え直すメディア「アートと都市と公共空間」
“アートの力で社会を開く”に挑戦する実務者のためのメディア「アートと都市と公共空間」。2023年4月に開設し、実例紹介やコラム、インタビューなど、アートと都市と公共空間にまつわるコンテンツを展開しています。

サイトを運営しているのは、横浜市芸術振興財団。発起人の杉崎さんは、メディアの設立趣意についてサイト上で以下のように説明しています。
「アートと都市と公共空間」は、都市の公共空間において芸術を含む環境づくりを実践したいとき、実務者の玄関となるメディアです。主に行政や企業といった公共空間を所有・運営・管理されている方、それを計画や研究等で支援される方、アーティストやアートマネージャーといった現場実務される方を対象とし、サイトを通じた情報交換を通じて、行政等の窓口や専門家の見える化をすることで、地域の公共空間におけるアート導入の促進を目指します。
公共R不動産としてもテーマ・趣旨に共感し、メディアにて記事寄稿をさせていただきました。その後もこのテーマに関心を寄せるメンバーで継続して探求するための研究会を立ち上げ、アート・都市・公共空間をまたがる様々なテーマに対してリサーチや研究を行っています。
アートと都市と公共空間研究会メンバー(2025年3月時点、順不同)
杉崎栄介(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団職員)
岡田潤〈東京大学 大学院新領域創成科学研究科 ハビタット・イノベーション研究社会連携講座 特任助教〉
山下裕子〈ひと・ネットワーククリエイター/眺めニスト〉
飯石藍(公共R不動産/株式会社nest)
松田東子(公共R不動産/株式会社スピーク)
今回は、熊本市のまちなかに位置し、まちと繋がって様々なプログラムを展開している熊本市現代美術館(以下「CAMK」)の取り組みについて取材した最新記事を紹介。その後プログラムの裏側や美術館での活動について、熊本市現代美術館副館長の岩崎千夏さんにお話を伺ったトークセッション(2025年1月27日開催)の様子をお届けします。進行は研究会メンバーの山下裕子さん、岡田潤さんです。
※本編を読んでいただく前に、こちらの記事を読んでいただくことをお勧めします。
まちの未来を美術館で考える-熊本市現代美術館の取り組み
山下:改めて岩崎さん、本日はありがとうございます。取材を通じて、改めてCAMKの取り組みの意義深さや、美術館にとどまらない活動の深さに驚かされていました。
ここからは記事で取り上げたトピックや、記事には書ききれなかった裏話も含めて岩崎さんにお伺いしようと思います。
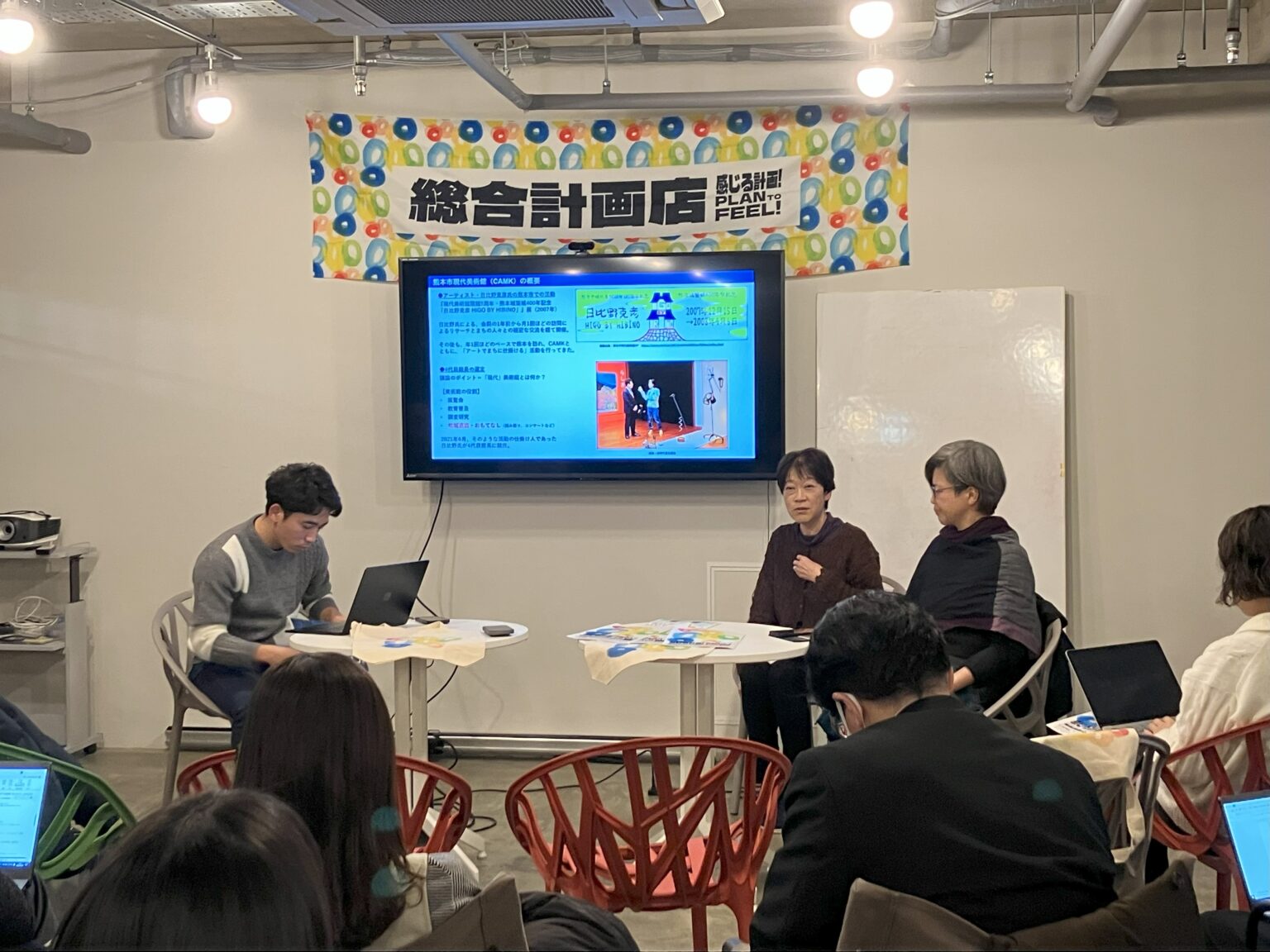
山下:では私からいくつか質問させていただきます。「ご用聞き」という活動が「業務的」になったことで美術館の業務が進めやすくなったのではないか、というまとめを記事上ではしていますが、実際のところはいかがでしょうか?
岩崎:「ご用聞き」の前から、美術館には悩み相談や雑談をしに訪れる市役所職員が一定数いました。以前は、彼らの話を聞いたり相談に乗ったりしている時間は、美術館の中では業務とは見なされていなかったんですが、そういった相談事や対話そのものに「ご用聞き」という名前がつくことで、「業務のようなもの」として周りが受け入れてくれるようになりました。この動きを進めることで、館の中に閉じていた美術館の活動そのものを外に開いていくことができるんじゃないかなという期待も持っています。
そもそも、アートを鑑賞する、アートに触れるという行為は、他者の表現を通じて自分の思考を整理することなんです。その考え方は、アート界隈の人にとっては当たり前のことなんですが、あまり一般的なものではないかもしれません。しかし「ご用聞き」という取り組みは、その行為そのものがアートであると感じています。つまり、業務の話や困りごとを聞いてもらうという行為を通じて、自らの業務や考え方そのものを振り返る機会になる。そういう心が動く体験を繰り返し、体感していただけたら、美術館やアートというものの敷居がもっと低くなるのではと思っています。

岡田:取材を通じて、岩崎さんをはじめとしたアートに携わる方々は、社会のことを違った角度から見る目や、面白がる視点にセンスや鋭さがあるなと思いました。都市計画の分野では、どうしても大きな視座・大きな問題に重きが置かれがちなんですが、アートの領域では、そこで起きる小さな事象も忘れないし丁寧に拾い上げていく、という別角度からの深さがあるなと感じていました。
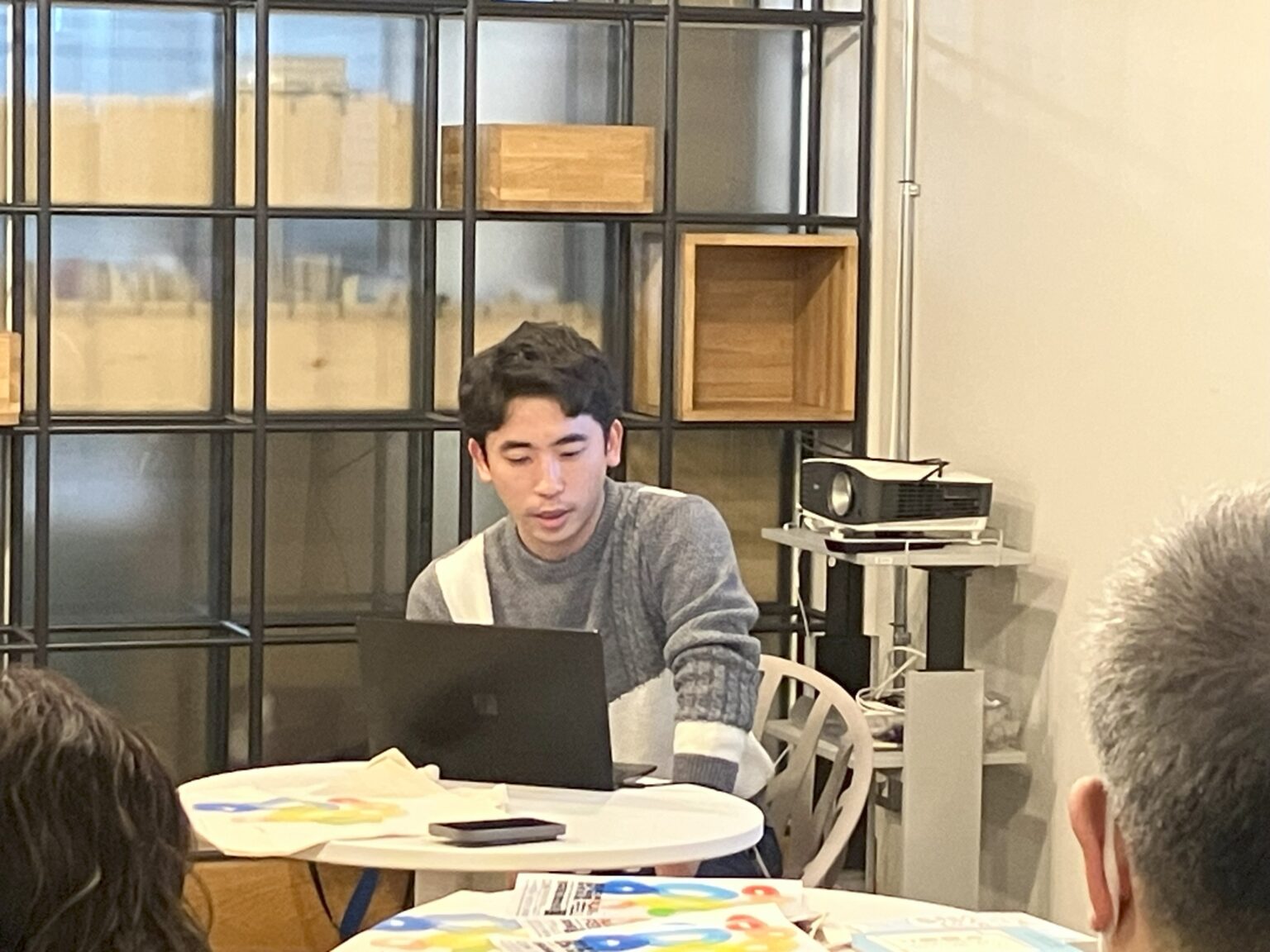
岩崎:行政は堅苦しい、美術館は柔らかい、という分け方をする人もいますが、市役所職員の皆さんって1人1人と話すとすごく誠実で真面目な人たちなんです。しかし、批判を受けないようにしなければいけない、決まったことは必ずそのとおりにやらなければいけない、という思考に縛られているように見える。一見当たり前だと思ってしまっている状況に対して、本当にそうなの?とか、どうしてもそれをやる必要があるの?といった「問い」を立てることがアートの意味なんじゃないかなと。「ご用聞き」はその問いかけをやっているんだなと思っています。
例えば市役所へ伺ったときに、とある行政担当者が「基本計画を作るにあたって冊子を作らなきゃいけなくて」と言っていました。それを聞いた日比野館長は「どうしても冊子じゃなきゃいけないのですか?」「それよりも、市民に伝わることが大事なんだよね」と返答して、それを聞いた担当者はハッとするんですよね。本質を掴んだ上で、そのためには何から考えていけば良いのかという思考に切り替わったんです。
アートは、ある状況や課題をどう面白がって乗り切れるかという視点をくれるもののような気がしています。課題にまともにぶつかり合うと大変ですが、その課題をくねくねと避けながら、いつの間にかゴールに到達した、みたいな。そういう思考のプロセスを楽しめるような人が増えれば、結果良いまちになると私は思っています。
まちを「知る」よりも「感じる」ことから始まる
飯石:「感じる計画!総合計画展」の開催を経て、市民の方の反応はいかがでしたか?展示後に何か変化は起きましたか?
岩崎:変化があったかはよくわかりません(笑)私としては、展示を通じて、市民は総合計画を知ることではなく「感じてもらう」ことに重点を置いていました。
会期中、総合計画の中のテーマ(8つのビジョン)について考えて作品を作るというワークショップを開催していたのですが、そこに参加していた親子がいたんです。最初はお子さんが一生懸命取り組んでいましたが、いつのまにかお父さんの方が熱中して作品作りをしていた、その風景がとても良いなと思ったんです。大人も子どもも、普段の生活では忘れがちなことに改めて気づく、その機会そのものが大事なんじゃないかと思っています。
ワークショップはのべ800人が参加しました、その人たちが一瞬でも「良いまちってなんだろう」「信頼・愛・希望(総合計画のビジョンの一部)ってなんだろう」といったことに考えを巡らせていく中で、何か感じてくれていたらいいなと思っています。
参加者:ご用聞きや総合計画展が終わった後、行政内の変化はありましたか?
岩崎:総合計画展終了後、市役所のこどもに関する基本計画には「感じる!総合計画展」を踏まえた要素が盛り込まれました。さらに、市役所職員の人材育成プログラムでも「アートを使った人材育成」という項目が盛り込まれています。少しづつではありますが、行政のかたちが変わりつつあるように思います。
岡田:CAMKのように、まちとつながる美術館のようなあり方は、他の美術館にも展開し得るとお考えですか?
岩崎:そもそも、美術館は何のためにあるのか?ということから考える必要があると思います。美術館は作品を見にいく場所ではなく、作品を通じて自分と対話し、考えを整理したり発想を膨らませたりする中で、多様な考えや価値観を受け入れられるようになる心を育む場所なんです。
そういった観点で、美術館というところは市民の心を育むために価値がある場所だという共通理解を、行政や市民の皆さんに持っていただければ、今後美術館としてできることも広がっていくのではと思っています。
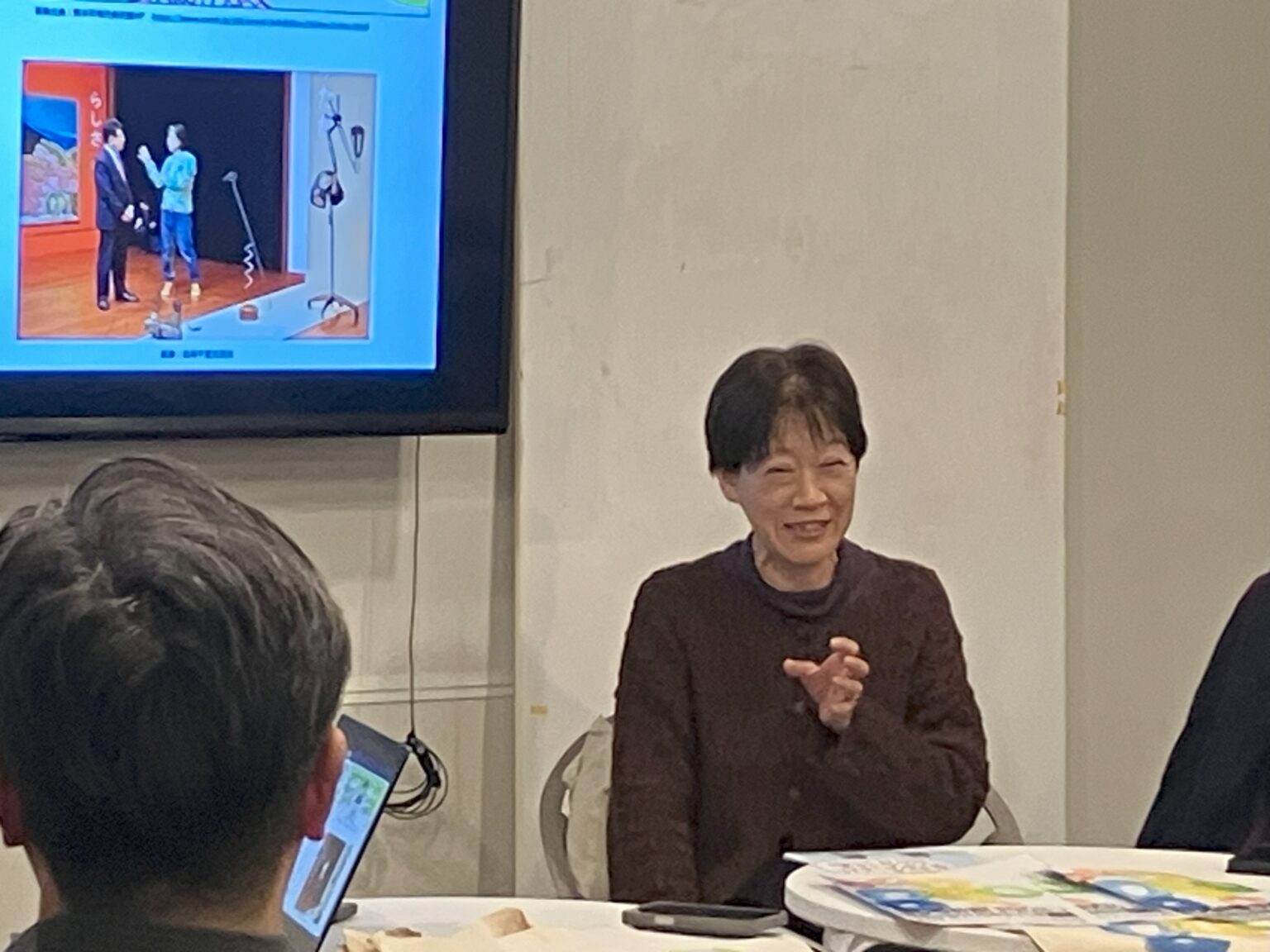
山下:おっしゃる通りですね。ちなみに私は熊本市のエリアマネジメントアドバイザーを拝命していますが、今年度から文化政策課の方からの依頼で「熊本市文化芸術推進基本計画」の委員も拝命しています。これまで文化芸術の委員会に都市側の専門家は入っていませんでした。それ故にこれは大きなニュースではないかと。まちが、いろんな人にとってフィールドにしてもらったり、異なる領域・分野の人が出会うきっかけにもなるといいなと思っています。
参加者:改めてすごい取り組みだなと思って話を伺っていました。そもそもこういった文化的なものを受け止められる市民の文化度の高さ、のようなものが熊本市にはあったんでしょうか?
岩崎:CAMKは商店街の中にあります。3つの商店街がネットワークされていて、さらに商店街の店主たちがとてもフットワークが軽くて、新しい試みを面白がって乗っかってくれたり、アート的な活動を受け止めてくれるんです。まち全体の文化度が高いかはわかりませんが、少なくともCAMK周辺の商店街にはそういう器量のある方が多いなという印象はありますね。
参加者:CAMKのような美術館を他のまちで作ろうとしたら、どんな機能や要素が必要だと考えますか?
岩崎:大前提として、美術館を運営するチームと、企画展示等を進めるチームの連携が取れていることが重要だと思っています。両チームの間をつなぎ、まずはチーム同士が仲良くなる状況を作ろうと意識していましたね。
2003年に美術館に対して指定管理制度が導入され、私たちの財団が運営から外れるかもしれないという危機に襲われたのですが、これは職員同士の結束が深まった大きな契機となりました。学芸員だから、総務だから、といって美術館の内側を向いている場合じゃない、という状況の中で一体感が生まれたのです。
将来的に運営組織が世代交代・新陳代謝することも見据えて、今の熱量を知らない世代の方が関わったときに、そのチームをどう維持できるかは今後の課題になっていくと思っています。
杉崎:岩崎さん、貴重なお話を本当にありがとうございました。日本国内でここまで地域と連動している取り組みができている美術館ってほとんどありません。通常、地方の美術館に勤務する学芸員は業務量が多いにもかかわらず、人員が限られています。地方の小さな美術館に行くと、学芸員が1人しかいないのでその人が企画展も常設展も全部やるという状況が当たり前になっています。一体どのようにこれらの展示や様々な企画を動かしているんでしょうか。
岩崎:CAMKでは、総務も学芸も関係なく、全員が企画やプロジェクトに関わっています。例えば、会計班が子育て広場の運営をしていたり、管理班がストリートアートの音楽プログラムを手がけていたり、学芸員だけど書籍イベントを手掛けていたり。全員がマルチタスクで動いています。
杉崎:なるほど。。岩崎さんはサラッとおっしゃっていますが、美術館運営としてはかなりすごいことをやっていらっしゃると感じています。
昨今の公共施設では、PFIやコンセッション※といった官民連携の手法が美術館や文化施設などにも導入されてきています。しかし岩崎さんのお話を伺うと、コンセッションが向いている事業とそうじゃない事業があるなと。特にCAMKの地域連動での取り組みについては、コンセッションではなく行政に近い立ち位置で非営利中心にやっていくという形態もあるんだと感じました。もちろん大型の美術館で利用料を払っていただいて収益を成り立たせる美術館もあっていいし、ギャラリースペースを貸し出すことで収益を得る形式もあっていい。今回の話は、そういった美術館や文化施設運営における新たな選択肢を見せてもらったような気がします。
※コンセッション:施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式
山下:改めて岩崎さん、本日はありがとうございました!
岩崎 千夏
熊本市現代美術館 副館長
1968年熊本生まれ。1997年、美術館の建設準備が始まった年に運営母体である財団法人に採用された一人目のプロパー職員。総務職員を経て、指定管理者制度をくぐり抜け、現在は主に学芸班の取りまとめ役、管理班の叱咤激励役、会計班の相談役、館長の補佐役、ソト・タテ・ヨコの調整役など、つまりなんでも屋。因みに熊本市現代美術館は2002年に開館し、昨年20周年を迎えた。
杉崎 栄介
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 職員
1999年から同財団で働く。地域の文化施設、フェスティバル等を担当、横浜市役所開港150周年・創造都市事業本部への派遣を経て、2007年にアーツコミッション・ヨコハマを立ち上げ17年間担当。現在は横浜市民ギャラリーあざみ野館長。協働・共創、まちづくりに関心を持ちながら、文化芸術振興の仕事をしている。
遊休不動産の文化芸術利用計画の策定、各種助成制度の設計運用、イベント制作やアーティスト支援の経験を活かして、WEBサイト「アートと都市と公共空間」の企画制作を行う。
岡田 潤
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 ハビタット・イノベーション研究社会連携講座 特任助教
神奈川県藤沢市出身。2019年東京大学工学部都市工学科卒業。2024年東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻博士課程修了。2025年4月より現職。専門はアーバンデザイン・都市計画。博士論文のタイトルは「都市生活における余暇の時空間に関する研究 -都市計画への示唆-」。著書に『余韻都市』(共著、鹿島出版会)。
山下 裕子
ひと・ネットワーククリエイター/広場ニスト
2007年から富山市まちなか賑わい広場「愛称 グランドプラザ」のスタッフを経て、2014年から“ひと・ネットワーククリエイター”として活動開始。地域の余地を“用がなくても日常的にそこに行こう”と感じられるような機運醸成づくりの際に、地元の皆様の伴走者的な立ち位置で活動中。著書に『にぎわいの場 富山グランドプラザ-稼働率100%の公共空間のつくり方』(学芸出版社)、『生きた景観マネジメント』(共著・鹿島出版会)、『コンパクトシティのアーバニズム』(共著・東京大学出版会)







