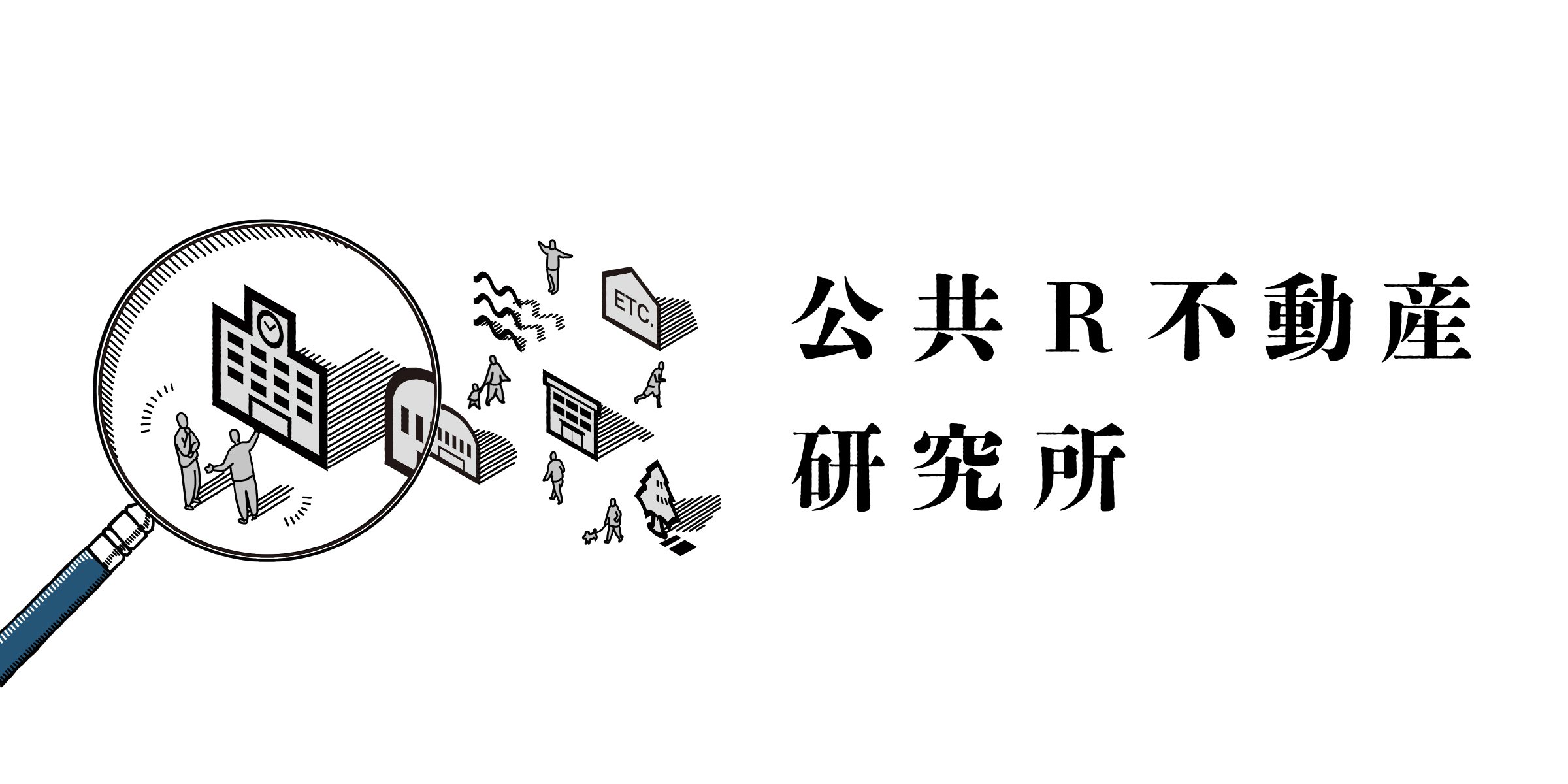山口情報芸術センター、通称YCAM。2003年の開館以来、メディアアートを中心に活動を展開してきた、世界的にも有名な施設だ。磯崎新の設計による巨大な建物のなかには、展示がされるギャラリーや、アーティストが制作や研究に利用できるラボ、演劇・ダンス、展示、コンサートや映画上映に使われるスタジオ、そして市立図書館などが整っている。そして近年は学校や地域と連携した活動も活発になっているようだ。その幅は多岐にわたっており、なかなか全貌を掴みきれない。
人口20万人に満たない地方都市に、なぜここにこのような施設が生まれたのか。そして何を目指しているのか。
なぜ山口にメディアアートの施設が?
YCAMのある場所には1990年代まで県立体育館・県立高校・市民球場があった。それらの移転に伴って跡地の開発計画が持ち上がったとき、山口市は郵政省(当時)が発表した地域情報通信活性化構想に基づいて調査を行い、ここを情報機能ゾーンとし「文化交流プラザ(仮称)」を作ることにした。

情報化社会を背景に「メディアアート」を軸とした構想が立てられた。国内ではまだ東京くらいにしかなかったコンセプトの施設を作るにあたって、行政の計画チームは、オーストリアのアルスエレクトロニカ(1979年創立、1996年センター開館)など国内外の先進的な施設を視察した。それらの発展形として計画されたのがYCAMだ。大規模なインスタレーションが制作できるスタジオなどの先端設備に投資した。また、財団法人山口市文化振興財団を設立し、施設を使いこなすための組織体制や予算も整えた。
YCAMスタッフの菅沼聖さんは「この規模の地方都市で、ここまで先進的な公共文化施設が実現し、現在まで20年間実験性を失わず継続できているのは奇跡だと思います。実験的な場をつくる際の参考にと外からの視察も多いYCAMですが、かなり特殊なのでまるごとコピーするのは難しいかもしれません」という。読者の皆様の出鼻を挫くようだが、ひとつめの問い「なぜここでこんな施設が生まれたのか」には、再現性のある答えがないのである。

地方都市でこそやるべき実験と種蒔き
東京や大阪ではない、山口という地方都市にこのような実験的な施設は本当に必要なのだろうか? 地方都市だからこそ必要なのだと菅沼さんは語る。「大都市では市場原理の上で実験的なイノベーションが起こる土壌がありますが、地方では基盤となるマーケットそのものが成立しない場合も多々あります。様々な社会課題に直面する地方都市において、YCAMのような公共文化施設が実験性を担い、都市機能の更新をしていく可能性は十分にあります。」
例えばYCAMでは、社会的な需要が大きくなる前から、メディアリテラシー教育が重要だと考えて注力してきた。当初は開発したコンテンツを使ってもらおうと学校に売り込んでもなかなか理解してもらえず、自らワークショップなどを開催するしかなかった。しかし、あるとき急に風向きが変わった。GIGAスクール構想(2019年〜)に伴う学校でのタブレット導入である。教育現場では急に1人1台タブレットが提供されても、それを使う準備ができていない。そこでYCAMが蓄積してきたメディアリテラシー教育のノウハウに注目が集まった。時代の潮流が追いつき、ようやく足並みが揃うようになった。
「必要になってから作るのでは遅い。種蒔き期間が重要です。でも、何につながるのかわからない状態で実験を続けるには、社会にどう説明し、肯定してもらうのか、なかなか難しい面もあります。」
現在、山口市では、小中学生が、タブレットで地域図鑑をつくることができる「360°図鑑」という授業プログラムがあるが、これはYCAMが2015年から独自の企画として実施してきたバイオ・リサーチプロジェクトで制作されたウェブアプリケーション「森のDNA図鑑」のノウハウを転用したものだ。無論、このような転用は最初から計画されていたものではなく、アイデアが人から人へ流転していく末に行き着いた結果である。
本気で実験をできる環境を
YCAMには約40人の常勤スタッフがいるが、そのうちメディアアートに関する調査・開発などを担う「YCAM InterLab(インターラボ)」のスタッフが約20人を占める。キュレーター、プロデューサー、エデュケーター、デザイナー、照明、音響、映像、デバイス開発などの専門性を持つスタッフが、活発に制作し、そして誰かがやりたいことを本気でサポートするエンジンとして機能する。彼らがいることで、コラボレーターであるアーティストやクリエーター、研究者、市民が考えていることを本気で実現することができる。

メディアテクノロジーやパーソナルファブリケーションの技術はどんどん進化し、社会での在り方も変わっていく。それについて行くため、新しい設備に投資するための予算もしっかり確保されている。
2015年に先述のバイオ・リサーチプロジェクトを進めるために、館内にバイオラボを設置した。情報技術の発達がDNA解析などの低コスト化に寄与にしているという点で、メディアとの関係も実は深い。「新しいことを試すときには、可能性を探るために、いきなり外部の専門家を連れてくるのではなく、自分たちでリサーチしながら試してみている。ラボスタッフが専門家との共通言語を持てるようになると、良いコラボレーションにつながります。」
実験性を失わないための工夫が、施設の随所にも現れている。例えば劇場として使われることの多い、スタジオA。当初は客席数2000席という要望があったが、それでは集客力や収益性の高い企画しか実施できなくなると考え、あえて大幅に客席を減らした。代わりに、新作の制作がしやすくするためのマージナルな空間や、優れた音響環境を実現するための設備に投資した。この結果、劇場でありながら、インスタレーション作品の展示や、運動会イベントなど、劇場の枠組みに留まらない企画を実現できるようになった。

偶然の関わりの余地を残す施設のあり方
展示がされている共有スペースやギャラリーの入り口には、通常美術館で人数や入場料を管理するような「もぎり」のスペースがない。基本的にチケットレスで誰でも入れてしまう。これも実は重要だという。もぎる場所があると、人数や収益をいつも気にしないといけなくなる。何気ないフレームが事業内容を規定してしまう。
YCAMには市立図書館が併設されている。前には広場(中央公園)もある。わざわざ展示を見に来る人だけでなく、たまたま来た人、目的的ではない人が関わってくる余地を作るための工夫でもある。

天井のルーバーは、容易にものを吊るしたり壁を立てたりできるようになっている。ちょっとした造作をするのにいちいち時間がかかったり外注していたりすると、創作のスピードも自由度も落ちる。自分たちである程度何でもできる環境というのが必要である。速度と柔軟性がクリエイターからのリスペクトに繋がる。

YCAMスタッフの渡邉朋也さんは、実験的な施設のあり方を「制度化されていない遊び場」と表現する。テックの応用可能性の高さを活かして、見た人によって異なる好きな使い方をされるような場所を創りたいという。何をやるのか決まっていない場所こそが、幅広く外部の市民やクリエーターを惹きつけているという。
YCAMに来る人だけを対象にしていると、知らず知らずのうちに線引きをしてしまう。それを越境することで強度が上がっていく。学校との連携についても、市内に山側から海側まで多様な学校があるなかで、授業というフォーマットに落とし込むことでいろんなフィードバックが得られるという。
「実は山口には、草の根でまちづくりに近い活動をやってる人がたくさんいる。そういう人に出会ってやったりすると、意外と目指している方向が近かったりして、学ぶことは多い。まだまだ未知のコラボレーターが眠っているんです。」

地域とともに、持続していくために
先述の通り、アートクリエーションの知見がいろんなところで使えることがわかってきた。YCAMではメディアアートの作品精度を上げていく中核の活動と並行して、地域に寄り添い還元していく展開とのバランスを探っている。
YCAMの基本的な資金源は文化政策関係の予算だけではなく、教育やまちづくり関連の予算がつくようになっていく。これは持続のための苦肉の策ではなく、領域を越境して活用されていくという意味でむしろ目指すべき展開といえるだろう。
例えば、空き店舗を活用してまちの賑わいを作っていこうという中心市街地活性化事業のなかで、YCAMの知見を活用した外部連携プロジェクトを実施している。
ひとつめはJR山口駅近くにある「YCAMサテライトA」。YCAMには作品所蔵機能がないので、過去のインスタレーション等は展覧会期終了後には基本的に解体されてしまう。そこで、常設的に展示する場所をまちなかにつくったのだ。


ふたつめがやまぐちアートコミュニケータープログラムとして実施されている「架空の学校アルスコーレ」。参加型で作品をつくって商店街の中で展示する取り組みなどを通して、「アートコミュニケーター」の育成に取り組んでいる。まちの中に文化活動が滲み出ていく時、しばしば予想できないことが起こってしまう。そのような時にソフトランディングさせるための人材育成だ。アートと街をつなぐ存在がいないと、ハレーションが起きてますます離れていってしまいかねない。
3つめが「アルスコーレ」の活動拠点、tog。もともと研ぎ屋だった小さな建物を2022年に改修、2023年から活用している。できる限りメンバー自身の手で場を作っていくことによって、「人と人との関係を編み直す機能」を担っている。椅子作りのワークショップ、映像見る会、中学生がコーヒー入れてみるお店など、日によって場所の在り方がガラッと変わる体験を、ゲストに来てもらって実現する場所になっている。「今日はなに屋さんなの?」と気になって訪ねて来る人が応募してプレーヤーに変わっていく。世代はバラバラ、市内だけでなく遠方からわざわざ訪ねてきている人もいる。プロジェクト自体は発表会で終わりにしているけど、せっかく場所があるから、やりたいと、自主的な活動が続いている。

まちとアーティストの断絶を補う取り組みは、かつてはプログラムとしてやっていたが、仲間を増やしコミュニティをつくる方向に拡がっている。YCAMやサテライトA、togなど、用途や設備が異なる拠点を複数持つことで、市民の入口が増え、興味を持ってくれた人が他のものを見たり、やりたいことを練っていく動線ができていく。
YCAMキュレーターの西 翼さんは取り組みの意義をこう語る。「文化は独立したものではなく、宗教があった上での宗教画とか、聞く人がいる中での音楽とか、取り巻くコミュニティがあってのものと考えています。素晴らしいアーティストが来ることだけが文化ではない。では、誰が文化的な生活を支えるプレイヤーになるのか? YCAMスタッフやコミュニケーターだけでいいのか? 文化は誰かが与えてくれるものなの? という問いを大事にしていきたい。YCAMを花が咲く場所だとすれば、その根っこを張る作業。YCAMが生み出すものを、山口の財産にしていく、仮にYCAMがなくなったとしても、文化と人が残っていくための取組みです。」

YCAMの本質は「まだわからないこと」ではないか
記事の冒頭で、YCAMの活動の全貌が掴めないと書いたが、3人のお話を聞いても、一言で表す言葉は見つからず、ますますモヤに包まれたような気分にさえなる。しかしそれこそがYCAMの本質なのではないか、と思うようになった。
すぐに成果が出るわけではないことに取り組むのはもちろん容易ではない。求められることを見極め、理解を得て還元していくことが不可欠である。
YCAMは地方都市の環境のなかで特殊性と普遍性を見出し、商業性を超えて、行政の区分を超えて、立場も超えて、「まだなんだかわからないこと」をゆっくりじっくり温めてきた。明確なテーマと裾野の広さを両立させながら持続する施設のあり方は、全国の公共文化施設の大きなヒントになるかもしれない。